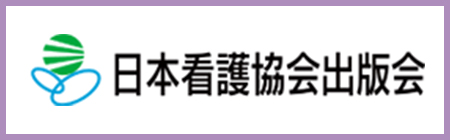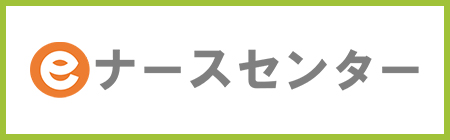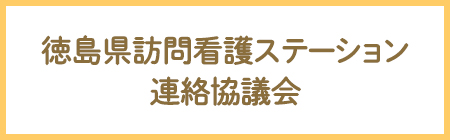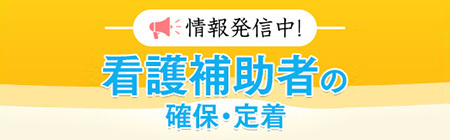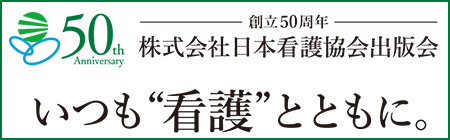医療・看護安全相談窓口
医療・看護安全相談窓口のご案内
看護職の皆さんの医療・看護安全対策に関する質問や相談をお受けします。医療・看護の安全を確保するための具体的な情報の提供・助言等もいたします。
また、医療事故が発生した場合の対応及び看護職の支援についても相談をお受けしております。公平で中立的な立場で対応し、相談者の問題解決を支援します。回答にはお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。ご連絡をお待ちしております。
主な相談内容
- 指示出し、指示受け
- 患者誤認防止
- 誤薬の防止
- 転倒転落の防止
- 医薬品・医療機器の安全使用
- 医療事故発生時の対応
- 医療・看護に関する苦情や相談
相談窓口
お電話でのお問い合わせ、または直接ご来館頂いてもどちらでも可能です。
- TEL:088-631-5544
- FAX:088-632-1084
- 時間:平日9:00~17:00
- 相談受付者:徳島県看護協会担当
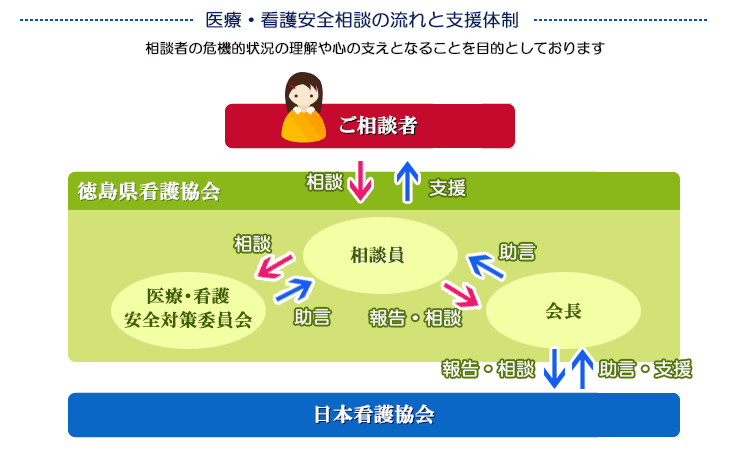
医療・看護安全相談例
- 新人看護師として4月から急性期病院で働いています。多忙な業務の中、誤薬しないためにはどうしたらいいか不安があります。注意点など教えてください。
- 患者さんに間違った薬を投与しないためには、薬の管理、投与の確認、患者の識別など様々な予防策を講じていく必要があります。
看護師が誤薬を防止することは、患者さんの安全が確保され医療事故の防止につながるため結果的に医療の質の向上につながります。与薬までの確認の手順として「与薬原則の6つのR(正しい患者、正しい薬物、正しい目的、正しい用量、正しい投与方法、正しい時間)」と指さし呼称やダブルチェック、患者さん本人と確認をするなどしてミスを防いでいきましょう。
誤薬防止を実践するために看護師は知識と技術を習得し、常に注意深く業務を行っていくことも大切です。
- 「患者参加」について院内でその考え方をどのように共有し、具体的な取り組みにつなげればいいでしょうか?
- 「医療安全」のために患者さんやご家族参加が必要なことについては、次第にその認識が広がってきています。
- 患者さんやご家族との情報共有の重要性を認識する。
患者さんは、自身の疾患や治療、それに関するリスクについて、十分な情報を持つことが不可欠です。例えばアレルギーの有無などの情報を認識していないと処方された薬が適切かどうか気付くことはできません。 - 情報共有の工夫をする。
患者さんが分かりやすい言葉を使う、具体的なイメージが持てるように説明する、繰り返し伝えるなどが必要です。 - 事故防止対策に患者参加の視点を加える。
ポスターやパンフレットを活用し、患者さんやご家族に協力してもらえる事故防止対策を考える。 などに取り組んでみてください。
- 患者さんやご家族との情報共有の重要性を認識する。
- 患者さんが退院される際に中止薬を返却し忘れました。お電話したところ、「薬はいらないから捨てておいてくれ」と言われました。このような場合インシデントレポートは記載したほうがよいでしょうか?
-
インシデントアクシデントレポート作成の意義として
- 患者安全確保
- リスクの分散
- 透明性の確保
- 正式な支援
- システム改善

 入会案内
入会案内 検索
検索 アクセス
アクセス お問い合わせ
お問い合わせ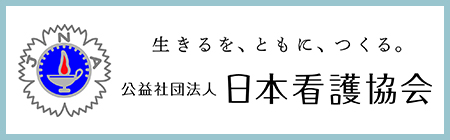
![公益社団法人日本看護協会インターネット配信研修[オンデマンド]](https://tokushima-kangokyokai.or.jp/wp-content/themes/tokuna/assets/img/common/ft_bnr02.jpg?1559026443)